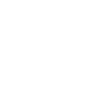公開日 2014年2月10日
更新日 2024年10月9日

国民健康保険
医療保険には、国民健康保険、社会保険、官公庁や学校の共済組合、船舶等の国民健康保険、医師や土木建築業者が加入する国民健康保険組合などのほか、75歳以上の方等が加入する後期高齢者医療保険があります。
市民のみなさんは、必ずいずれかの医療保険に加入して保険税(料)を納め、病気やケガをしたとき必要な保険給付を受けています。
- 国民健康保険の加入・脱退等の手続きについて
- 国民健康保険の受けられる給付
- 一部負担金の減免額など
- 後期高齢者医療保険について
 (長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ)
(長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ)
会社などを退職された方へ
医療の自己負担は、70歳までの方は3割、70歳から75歳までの方は3割又は2割です。
社会保険資格喪失証明書と身分証明書をご持参のうえ、手続きをお願いします。
2018年4月から国民健康保険制度が変わりました
国民健康保険制度は、日本の国民皆保険を支える重要な社会保障制度ですが、「加入者の高齢化により医療費が増えている」「小規模保険者(市町村)が多く、財政が不安定になりやすい」などの構造的な課題を抱えています。
そこで国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担う(保険者となる)ことになります。
ただし、市町村は引き続き資格管理、保険給付、保険税(料)率の決定、賦課・徴収、保険事業などを行いますので、市民の皆さんの各種手続き等の窓口であることに変更はありません。
制度改革の柱
- 都道府県が市町村とともに国民健康保険(国保)保険者となり財政運営の責任主体となります。
期待される効果
- 財政規模が拡大し、国保財政が安定します。
- 市町村は医療費水準や所得水準に応じた納付金を負担することで、市町村間の公平な負担により財政が運営されます。
主な変更点
- 2018年10月以降、被保険者証に都道府県名が表記されます。
- 県内の住所異動であれば、高額療養費の上限支払い回数のカウントが通算されます。
- 保険税(料)の算定の基礎が変更となるため、保険税(料)率に影響が出る可能性があります。
県と市町村の役割分担
- 都道府県は、国保の収入と支出を管理し、国保の各種手続き等は、引き続き市町村窓口になります。