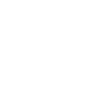公開日 2014年5月29日
更新日 2025年5月19日


児童扶養手当は、父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当を受けることができる方
児童(児童が18歳に達した場合で、政令で定める心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の者。)を養育している父母や、父母にかわってその児童と同居し養育している人で、国籍は問いません。申請者および扶養義務者の扶養親族等の人数に応じた所得制限があります。
支給対象者の条件
- 児童を監護している母
- 母が監護していない場合または母がない場合の養育者
- 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
- 父が監護していない、若しくは生計を同じくしていない場合または父がない場合の養育者
児童の条件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
児童を監護(養育)していても、手当を受けることができない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母が婚姻の状態にあるとき。婚姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある等当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)となった場合も含みます。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童の父または母の配偶者(事実婚、内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)
手当を受ける手続き
はじめて申請される方
手当を受けるには、福祉課で請求の手続をしてください。市長の認定を受けることにより支給されます。なお、請求前に母子・父子自立支援員との面談を行っていただき、ひとり親家庭の認定を受ける必要があります。
- 交付の日から1か月以内の戸籍謄本(離婚後の母又は父と子の戸籍謄本、または子の入籍後の戸籍謄本)。手当の支給は請求された月の翌月分からのため、戸籍謄本が間に合わない場合は、離婚届受理証明書や調停調書、審判書又は判決書の謄本(確定証明書を添付のもの)をご用意ください。
- 請求者と児童の保険証等(有効期限内の健康保険証、マイナ保険証、資格確認書など)
- 請求者の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
- 請求者と児童と扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
- その他必要書類(ケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください。)
すでに手当を受けている方
毎年8月に現況届を提出し、支給要件の審査を受けます。提出されないと11月分以降の手当が支給されず、2年間届けをしないと受給資格がなくなります。
手当を受ける期間を延長する方
児童扶養手当の支給は、対象児童が18歳に到達後の最初の3月31日までですが、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳の誕生月まで支給期間を延長することができます。障がいの認定には届出書の提出に加えて、原則として診断書が必要となりますが、児童が特別児童扶養手当の支給対象となっているとき、または身体障害者手帳(1から3級)の交付を受けてるとき、あるいは療育手帳(A)の交付を受けているときは診断書が省略できます。
手当の支払い
市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)に、支給月の前月までの分が口座振替により支払われます。(11日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日となります。)
| 月日 | 支払内容 |
|---|---|
|
2025年5月9日(金曜日) |
3月から4月分 |
|
2025年7月11日(金曜日) |
5月から6月分 |
|
2025年9月11日(木曜日) |
7月から8月分 |
|
2025年11月11日(火曜日) |
9月から10月分 |
|
2026年1月9日(金曜日) |
11月から12月分 |
|
2026年3月11日(水曜日) |
1月から2月分 |
手当月額
児童扶養手当法等の一部が改正され、2025年4月分から児童扶養手当額が変更しました。
| 手当区分 | 手当月額 |
|---|---|
| 全部支給 |
|
| 一部支給 |
|
| 加算額2人目以降 |
|
支給制限
所得による支給制限
- 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。(児童扶養手当法等の一部が改正され、2024年11月から受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられました。)
- 扶養義務者とは、生計を同じくする(同居をしているなど)直系血族(父母、祖父母、曽祖父母、子、孫、曽孫)及び兄弟姉妹のことです。児童扶養手当では、住民票上世帯分離をしていても、原則同居している場合には生計を同じくしていると考えます。
- ただし、自宅が二世帯住宅(別棟など)になっており、民生児童委員の証明書や光熱水費の領収書等を添付した生計別申立書を提出し、扶養義務者と生活環境や生計が別であることが客観的に証明できる場合には、生計が別である人の所得は審査対象となりません。
| 扶養親族等の数 | 本人(父または母あるいは養育者) | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 |
4,260,000円 |
上記限度額に加算できる場合
(父または母あるいは養育者)
配偶者
扶養義務者
扶養親族1人につき
- 老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を加算する。
- 所得額(控除後の所得額)の計算方法は、所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除
| 障害者・勤労学生控除 | - | 270,000円 |
|---|---|---|
| 特別障害者控除 | - | 400,000円 |
| 雑損・医療費・配偶者特別控除等 | - | 当該控除額 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 請求者が父または母の場合は控除しない | 270,000円 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 子を扶養し、かつ所得が500万円以下 | 350,000円 |
公的年金給付等による支給制限
障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額が児童扶養手当として支給されます。障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分が児童扶養手当として支給されます。そのため、公的年金等を新たに受給する場合や年金の受給額に変更があった場合には、速やかに届け出てください。
- 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
- 障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
養育する児童が増減したときは手当の額が改定されます
- 対象児童が増えたときは、手当額改定請求書(戸籍謄本等必要書類添付)を提出してください。請求の翌月から手当が増額されます。
- 対象児童が減ったときは、手当額改定届を提出してください。減った日の翌月から手当が減額されます。
- 対象児童が18歳になったときは、18歳になった日以降の最初の3月31日まで手当が支給され、翌月から手当が減額されます。届出は必要ありません。
認定されている内容が変わったときは届出が必要です
次のように認定されている内容が変わったときは、届出が義務になっています。
- 資格喪失届は、受給資格がなくなったときに提出します。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
- 支給停止関係届は、扶養義務者と同居を開始したとき、又は同居しなくなったときや、所得の更生や修正申告等により手当額が変更となるときに提出します。
- 受給者死亡届は、受給者が死亡したとき、戸籍法の届出義務者が提出します。
- 氏名(住所、銀行口座)変更届は、それぞれ変更しようとするときに提出します。
- 証書亡失届は、手当証書をなくしたときに提出します。
- 証書再交付申請書は、手当証書を破損したり、汚したときに提出します。
- 辞退届は、手当の全部が停止されていて、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいときに提出します。
手当の一部支給停止(減額)措置について
手当を受給している方で、支給開始月から5年を経過する等の要件に該当した場合は、必要な書類を提出していただかなければ、一部支給停止(減額)措置の対象となります。次の要件に該当する方は、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び要件に該当することが証明できる関係書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障がいがあるとき。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
- 書類の提出をされなかった方は、手当の2分の1が減額されますので、必ず手続きをしてください。
- この届出は、手当の支給開始月から5年を経過する等の要件に該当したときと、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。
児童扶養手当の認定を受けた方へ
手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりですので、該当する場合には届け出てください。手当の受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。
- 結婚したとき。婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある等当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)となった場合も含みます。
- 扶養している児童の養育をしなくなったとき。(児童が引き取られたときや児童の死亡、行方不明など)
- 扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき。(母子生活支援施設、通所施設は除きます)また、里親に預けられたとき。
- 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金等があったとき。
- 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき。
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード