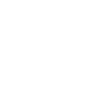公開日 2016年3月9日
更新日 2025年10月27日
土人形の里 中野市

土人形は、江戸時代末期から明治時代にかけて、日本全国各地で庶民生活に深く根をおろしていました。人形に込められた機知、格言、教訓などは、多くの子どもたちの教養となって、日本人の心の形成に大きな役割を果たしてきました。
中野市には、奈良家で制作されている「中野人形」と、西原家で制作されている「立ヶ花人形」があり、これらをあわせて「中野土人形」と呼んでいます。流入経路や特色が異なる二系統の土人形が、同一地域で今も昔ながらの伝統技法で制作されている地域は全国的に稀で、中野市が「土人形の里」と呼ばれる所以です。
中野人形(奈良家)
奈良家で制作されている「中野人形」は、江戸時代末期から継承されており、伏見人形を原型としたものが多く、主に縁起物や風俗物が作られています。
現在は奈良久雄氏(五代目)と奈良由起夫氏(六代目)により制作されています。

- 奈良久雄氏
- ふぐ乗り大黒

- 奈良由起夫氏
- 山姥
中野人形が年賀切手デザインに採用されました。
- 2015年 ひつじ
- 1981年 豊年どり
立ヶ花人形(西原家)
西原家で制作されている「立ヶ花人形」は、明治時代、三河の瓦職人の指導により創始され、歌舞伎を題材とした人形を中心に制作されています。
現在は、西原久美江氏(五代目)により制作されています。

- 西原久美江氏
- 八重垣姫
中野ひな市
毎年3月31日に行われる中野ひな市では、普段販売されていない貴重な中野土人形が抽選により販売され、全国の土人形ファンが集まります。
夕方には土人形を模した大灯籠びなが街を練り歩き、市内は賑やかな春の活気にあふれます。

※詳細は主催者である信州中野商工会議所の中野ひな市公式ホームページをご覧ください。