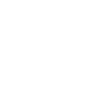公開日 2014年2月24日
更新日 2022年3月15日
全国的に児童虐待事例が増加しています。
児童虐待は、子どもの人権を侵害するだけではなく、時には子どもの命を奪ったり、子どもの心身の発達や人格の形成に大きな影響を与えてしまいます。これは科学的にも明らかになっています。
児童虐待には、以下の4つのタイプがあります。
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外にしめ出す など
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院へ連れて行かない、他人が子どもに暴力を振るうことなどを放置する など
性的虐待
子どもへの性的行為、性行為をみせる、ポルノグラフィの被写体にする など
心理的虐待
ことばにより脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV) など
体罰によらない子育てのために
令和2年4月から「しつけ」と称する体罰は法律で禁止されています。
これらは全て「体罰」です。
- ことばで3回注意したけど、言うことを聞かないので、ほほを叩いた
- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
- 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
- 掃除をしないので、ぞうきんを顔に押し付けた
- 言うことを聞かなかったので、クローゼットに閉じ込めた
- 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った
- やる気をださせるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした など
しつけと体罰はどう違うの?
- しつけとは、子どもの人格や才能を伸ばし、自立した生活をおくれるようにサポートしていくことです
- そのためには、体罰ではなく、どうすればよいのかをことばや見本を示すなど、本人が理解できる方法で伝える必要があります
子どもがもっている権利
- たたかれたりひどいことを言われない
- 元気に、健康に毎日を過ごして成長する
- 保護者の人から育てられる、守ってもらえる
- 自分の意見を言う、話を聞いてもらえる
これらは、世界の国々で約束されている「子どもの権利」です。誰からもこの権利を奪われることがあってはいけません。
体罰等によらない子育てのための工夫のポイント
子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう
- 相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえたという体験によって、子どもは落ち着いたり、大切にされていると感じたりします。
- 子どもに問いかけをしたり、相談をしながら、どうしたらよいかを一緒に考えましょう。
「言うことを聞かない」にもいろいろあります
- 保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがある、言われていることを子どもが理解できていない、体調が悪いなど、さまざまです。
- 「イヤだ」というのは、子どもの気持ちです。こうした感情を持つこと自体はいけないことではありません。重要なことでない場合、今はそれ以上やりあわない・・・というのも一つです。
子どもの成長・発達によっても異なることがあります
- 子どもの年齢や成長・発達の状況によって、できることとできないことがあります。また、大人に言われていることが理解できないこともあります。
- 子ども自身が困難を抱えているときは、それに応じたケアを考え対応しましょう。
子どもの状況に応じて、身の周りの環境を整えてみましょう
- 乳幼児の場合は、危ないものに触れないようにするなど、叱らないでよい環境づくりを心がけましょう。
- 子どもが困った行動をする場合、子ども自身も困っていることがあります。子どもが自分でできるような環境づくりを工夫してみましょう。
注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけてみましょう
- 子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しいこともあります。時間的に可能なら待つことも一案です。難しければ、場面を切り替えるなど、注意の方向を変えてみてもいいでしょう。
- 子どもが好きなことや楽しく取り組めることなど、子どものやる気が増す方法を意識してみましょう。
肯定文で分かりやすく、時には一緒に、お手本に
- 子どもに伝えるときは、「ここでは歩いてね」など、肯定文で何をすべきかを具体的に、また、穏やかに、近づいて、落ち着いた声で伝えると、子どもにも伝わりやすくなります。
- 「一緒におもちゃを片付けよう」と共に行ったり、やり方を示したり教えたりするのもいいでしょう。
良いこと、できていることを具体的に褒めましょう
- 子どもの良い態度や行動を褒めることは、子どもにとって嬉しいだけでなく、自己肯定感を育むことにもなります。
- 結果だけでなく、頑張りを認めることや、今できていることに注目して褒めることも大切です。
- また「ありがとう、助かったよ」と感謝の気落ちを伝えることで関係が良くなるきっかけにもなります。
保護者自身のポイント
- 否定的な感情が生じたときは、それは子どものどんな言動が原因なのか、自分自身の体調の悪さや忙しさ、孤独感など、自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみましょう。
- 深呼吸して気持ちを落ち着けたり、ゆっくり5秒数えたり、窓を開けて風にあたって気分転換するなど爆発寸前のイライラをクールダウン。
- 少しでもストレスの解消につながりそうな自分なりの工夫を見つけましょう。
- 保護者自身がSOSを出す勇気も必要です。
子育てはいろいろな人の力と共に
子どもと関わる中で、いろいろな工夫をしても、うまくいかないこともあります。そのようなときは、周囲の力を借りると解決することもあります
- 市区町村などが提供している子育て支援サービスの活用
- 子育て支援センターなどの利用
- 子育て相談窓口の利用 など
子育て中の保護者だけで抱え込まないように、まわりで接するみなさんも声がけなどを行い、孤立しないようサポートしていきましょう
子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか?
子どもについて
- いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
- 不自然な傷や打撲のあとがある
- 衣類やからだがいつも汚れている
- 落ち着きがなく乱暴である
- 表情が乏しい、活気がない
- 夜遅くまで一人で遊んでいる
保護者について
- 地域などと交流が少なく孤立している
- 小さい子どもを家に置いたまま外出している
- 子どもの養育に関して拒否的、無関心である
- 子どものけがについて不自然な説明をする
相談、連絡するには?
子ども相談室では、専門の相談員を配置して児童相談に応じています。
また、虐待を始めとする様々な問題を抱え、支援を必要とする子ども及びその家庭に対応するため、「中野市子どもサポート連絡協議会」を設置し、児童に関係する機関等が緊密な連携を図りながら支援を行っています。
子育ての大変さを全て一人で抱え込まないで、不安や悩みはぜひ相談してください。
連絡先
子ども相談室
0269-23-3191(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)
長野県中央児童相談所
026-238-8010
<関連リンク>長野県中央児童相談所のホームページ
児童相談所 全国共通ダイヤル
189 (いちはやく)通話料無料
児童虐待・DV24時間ホットライン
026-219-2413(24時間対応)
子ども児童虐待防止のシンボルマーク

オレンジリボンをあなたの胸に
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード