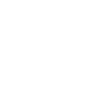公開日 2025年09月11日
更新日 2025年09月10日
高橋由一《第十一代山田荘左衛門顕善像》特別展示
幕末から明治にかけて、日本に洋画の道を切り拓いた高橋由一(1828-1894)。
本展示では由一が描いた中野市ゆかりの油彩肖像画《第十一代山田荘左衛門顕善像》(1883年)を特別公開します(期間中2点を展示替え)。
【会期】2025年9月26日(金曜日)~10月13日(月曜日・祝日)
【場所】常設展示室 ※要観覧料
【開館時間】午前9時~午後5時(火曜休館日を除く)

洋画家・高橋由一(1828-94)
高橋由一は下野国佐野藩(栃木県佐野市)の武士として江戸藩邸で生まれ育ちました。狩野派に学びますが、嘉永年間に洋製石版画を目にしたことで強い衝撃を受け、以降、洋画の研究を決意。幕府の蕃書調所に勤めて西洋画を研究し、1866(慶応2)年、イギリス人画家ワーグマンより本格的に油彩画を学びます。
明治維新後は民部省などに勤務し、1873(明治6)年に官職を退くと、画塾「天絵楼(のちの天絵社、天絵学舎)」を創設し、《花魁》(1872年)、《鮭》(1877年頃)といった代表作を描きます(ともに国の重要文化財)。
明治10年代後半からは、国粋主義運動の影響で洋画全般がふるわない時期となり、東北などの地方に活躍の場を求め、風景画や肖像画の制作を多数受注しました。江戸で中野市ゆかりの山田顕善を描いたのも、この時期です。
幕末から明治はじめの洋画黎明期にあって、ほぼ独学に近い環境で油彩画の技法や画法の研究を行った由一。和洋を超えた迫真に迫る表現を追求するとともに、日本初の美術館設立運動や美術雑誌の刊行など、洋画や美術の普及・発展を目指して幅広く活動を行いました。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード